![]() 消費者物価指数【しょうひしゃぶっかしすう】
消費者物価指数【しょうひしゃぶっかしすう】
小売物価統計調査から得られた商品及びサービスの価格を用いて、価格変動を時系列的に測定したもの。ある時点の世帯の消費構造を基準に、これと同等のものを購入した場合に必要な費用が物価の変動によって、どのように変動したかを指数値で表している。
消費者物価指数は「経済の体温計」とも呼ばれており、経済政策を的確に推進する上で極めて重要な指標となっている。
指数は、GDP統計のデフレーターとして利用されるほか、国民年金や厚生年金などでは、物価変動に応じて実質的な給付水準を見直す物価スライド制が法律によって定められており、この物価の動きを示す指標として消費者物価指数が使われている。このほか、賃金、家賃や公共料金改定の際の参考に使われるなど、官民を問わず幅広く利用されている。
石川県では、小売物価統計調査の価格データを用いて、金沢市の指数を作成している。
関連用語 ■ 指数(インデックス)【しすう(いんでっくす)】
関連用語 ■ 指数の基準年、基準改定【しすうのきじゅんねん、きじゅんかいてい】
関連用語 ■ 指数の計算方法【しすうのけいさんほうほう】
各月の指数の計算は、基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)で、次の式により算出する。
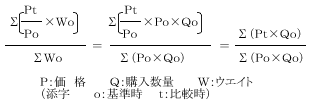
関連用語 ■ ウエイト【うえいと】
関連用語 ■ 上昇率【じょうしょうりつ】
指数の上昇率(前月比、前年同月比、前年比)をみるときは、二時点の指数を単純に引き算するのではなく、率を用いて、何パーセントの上昇(または下落)と表す。
上昇率は、次の式により算出している。
![]()
関連用語 ■ 前月比【ぜんげつひ】
当月の指数を前月の指数と比較した上昇率。直近の物価変動を表しているが、季節的な影響を受けた値なので、季節的な変動がある時はデータの見方に注意が必要。
関連用語 ■ 前年同月比【ぜんねんどうげつひ】
当月の指数を前年の同じ月の指数と比較した上昇率。同じ月の比較なので、季節的な影響を考慮せずに物価変動をみることができる。
関連用語 ■ 前年比【ぜんねんひ】
当年の年平均指数(その年の1月から12月までの各月の指数を単純平均したもの)を前年平均指数と比較した上昇率。1年間の総括的な物価の変動をみることができる。
関連用語 ■ 寄与度【きよど】
ある特定の項目の指数の変動が、総合指数の変動にどれだけ影響を与えたかを総合指数の上昇率の構成内訳で表したもの。
寄与度は、次の式により算出する。
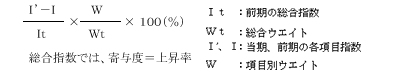
関連用語 ■ 寄与率【きよりつ】
各項目の寄与度を、総合指数の上昇率を100とした百分率で表したもの。
関連用語 ■ 生鮮食品【せいせんしょくひん】
消費者物価指数では、生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物の3つをまとめて「生鮮食品」と呼んでいる。生鮮食品は値動きが天候に左右されやすく、また、季節的な出回り状態によっても価格が変動するという特徴がある。
関連用語 ■ 持家の帰属家賃【もちいえのきぞくやちん】
家賃を住宅サービスの価格として指数計算に組み入れるときの方式の1つ。
持家に住んでいる世帯は、土地や住宅を購入したことにより、住宅から多くのサービスを受けている。そして多くの持家世帯が、住宅ローンなど住宅にかかるさまざまな経費を支払っている。そこで、持家に住む世帯が、自分の持家住宅から得られるサービスに相当する額を民営借家の家賃で評価したものが帰属家賃となる。
関連用語 ■ 接続指数【せつぞくしすう】
消費者物価指数では、基準改定によって採用する品目や計算に用いるウエイト(家計の消費支出に占める割合)を新しいものに更新するため、改定前と改定後の指数は厳密には内容が異なる。しかしながら、長期的な物価変動を時系列的に分析できるようにするため、基準改定時においては、新旧指数を接続する処理を行っている。
新旧指数の接続は、基準年における旧基準と新基準の年平均指数値(新基準は100)の比で、旧基準の指数を換算することにより行っている。接続処理は項目ごとにそれぞれ独立に行い、接続した指数による上位類指数の再計算はしていない。なお、前月比、前年同月比、前年比及び前年度比については、接続した指数により再計算することなく、各基準において公表された値をそのまま用いることとしている。また、各基準の基準年の1月の前月比、1〜12月の前年同月比、前年比及び前年度比についても、旧基準の指数によって計算されたものを用いている。
関連用語 ■ 地域差指数【ちいきさしすう】